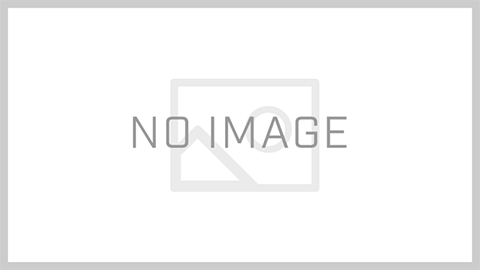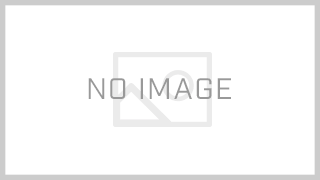強化学習1-6では、掛取引(かけとりひき)で使われる勘定科目「買掛金」「売掛金」「クレジット売掛金」の詳細と仕訳方法について学びます。
そもそも、掛取引とは?
掛取引(かけとりひき)とは?
掛取引とは、
代金を現金で精算せずに、後日まとめて精算する取引のこと
ドラマなどで常連のお客さんが「支払はツケで!」といって、支払いをしないままお店を出ていくのを見たことはありませんか。
この「支払はツケで!」の「ツケ」は「あとで支払う」という意味になります。
この「ツケ」を簿記の世界では「掛け」と言います。
掛取引は別名「信用取引(しんようとりひき)」ともいわれ、相手が支払をしてくれると信用できるからこそ成り立つ取引方法です。
ちなみに、代金を後日受け取るということは、相手がなかなか支払をしてくれなかったり、相手の会社が倒産してしまったりして、代金が回収できないというリスクを負うことになります。
掛取引の代金が回収できないリスクを想定して準備しておくお金を「貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)」といい、日商簿記3級試験ではよく出題されます。
貸倒引当金については、強化学習1-●で解説します。
商品売買の掛取り引きで使用する勘定科目
| 取引シーン | 勘定科目 | 勘定科目の詳細 |
| 商品の仕入 | 買掛金 (かいかけきん) |
仕入の際に、商品代金を後払いするときに使用。 代金を後で支払う義務を表す。(=負債) |
| 商品の販売 | 売掛金 (うりかけきん) |
商品の代金を後日受ける約束で販売したときに使用。 代金を後で受け取る権利を表す。(=資産) |
| クレジット売掛金 | 商品の代金をクレジットカード払いで販売した時に使用。 代金を後で受け取る権利を表す。(=資産) 売掛金と分けるのは、クレジットカード払いした代金の支払いが、取引先ではなく、カード会社(信販会社)になるため。 |
【掛取り引きの勘定科目名を間違えないために】
あああああ
「クレジット売掛金」は、平成31年度(2019年度)6月の検定から日商簿記3級の出題範囲となった新論点です。
買掛金(かいかけきん)の詳細と仕訳
勘定科目「買掛金」とは?
勘定科目「買掛金」とは、
仕入取引の際に、商品の代金を現金ではなく、後日精算(後払い)する約束で購入した場合に、後日支払う義務を表す勘定科目
ひとつの取引先から毎週のように仕入れをしていた場合、毎回現金で取引するよりも月末に一括で支払いをした方がお互いにメリットがあることがあります。
また、取引金額が億や何千万と高額の場合にも、現金で支払うより後日精算したほうが安全だったりします。
そのようなときに掛取引を行います。
勘定科目「買掛金」と似て非なる「未払金」
何かを購入した際に「代金を後払い」にしたことを表す勘定科目には「買掛金」の他に「未払金」があります。
「買掛金」と「未払金」の違いは次の通りです。
| 買掛金(かいかけきん) | 商品の仕入を後払いで行う際に使用 |
|---|---|
| 未払金(みばらいきん) | 商品売買以外の取引で後払いを行う際に使用 |
今回学習しているのは、商品売買で使用する「買掛金」です。
「未払金」は強化学習1-●で解説します。
仕訳の際に「買掛金」と「未払金」で迷わないようにしっかり違いを理解しておく必要があります。
勘定科目「買掛金」の所属グループ
勘定科目「買掛金」は「負債」の勘定科目に所属します。
基礎学習8で学んだ通り、負債のグループに属する勘定科目の定義は、【将来、お金やサービスを支払う義務】です。
勘定科目「買掛金」の借方貸方
勘定科目「買掛金」は、「負債」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 負債の増加 | 必ず、貸方に記録 |
|---|---|
| 負債の減少 | 必ず、借方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
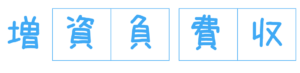
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
勘定科目「買掛金」の仕訳タイミング
日商簿記3級試験で出題される「買掛金」の仕訳のタイミングは次の3つです。
- 掛けで商品を仕入れたとき
- 買掛金の代金を支払ったとき
- 買掛金で仕入れた商品を返品したとき
勘定科目「買掛金」の借方貸方を例題とともに理解する
①掛けで商品を仕入れたとき
:買掛金(負債)が増えたときは右側の貸方
基礎学習6で学んだ通り、負債の増加は必ず貸方に記録をします。
例題1)A商店から商品¥5,000を仕入れ、代金は後日支払うことにした。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 仕入 | 5,000 | 買掛金 | 5,000 |
【仕訳解説】
- 商品の仕入れとあるので、「仕入の増加」と判断します。
- 仕入は「費用」の勘定科目なので、増加した場合には借方に記録します。
- 商品の代金は後日支払うとあるので、「買掛金の増加」と判断します。
- 買掛金は「負債」の勘定科目なので、増加した場合には貸方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
後払いで使われる勘定科目には「買掛金」の他に「未払金」があります。
後払いでも、商品売買(商品の仕入・商品の販売)のときに使うのは「買掛金」です。
「未払金」は商品売買(商品の仕入・商品の販売)以外の取引で後払いする際に使用します。未払金の詳細は、強化学習1-●で解説しています。
②買掛金の代金を支払ったとき
:買掛金(負債)が減ったときは左側の借方
基礎学習6で学んだ通り、負債の減少は必ず借方に記録をします。
例1)決済日となり、買掛金¥5,000を小切手を振り出して支払った。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 買掛金 | 5,000 | 当座預金 | 5,000 |
【仕訳解説】
- 今回は買掛金の支払いが取引内容となります。
- 「小切手を振り出して支払った」から「当座預金の減少」と判断します。
- 当座預金は「資産」の勘定科目なので、減少した場合には貸方に記録します。
- 買掛金の支払いが完了したので、お金を支払う義務がなくなります。よって、「買掛金の減少」の処理をします。
- 買掛金は「負債」の勘定科目で、減少した場合には借方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
例2)掛けで仕入れた商品のうち¥800分が品違いだったので返品した。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 買掛金 | 800 | 仕入 | 800 |
【仕訳解説】
- 今回は掛けで仕入れた商品の返品(仕入戻し)が取引内容となります。
- まず、返品なので「仕入の減少」の処理をします。
- 仕入は費用の勘定科目なので、減少した場合には借方に記録します。
- 返品した分の買掛金は、お金を支払う義務がなくなります。よって、買掛金の減少の処理をします。
- 買掛金は負債の勘定科目で、
- 減少した場合には借方に記録します。
- なお、複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
売掛金(うりかけきん)の詳細と仕訳
勘定科目「売掛金」とは?
勘定科目「売掛金」とは、
売上取引の際に、商品代金を現金ではなく、後日精算(回収)する約束で売った際に使う勘定科目のこと
勘定科目「売掛金」と似て非なる「未収金」
何かを販売した際に「代金を後で回収することにした(相手の後払いを承認した)」ことを表す勘定科目には「売掛金」の他に「未収金」があります。
「売掛金」と「未収金」の違いは次の通りです。
| 売掛金(うりかけきん) | 商品の販売代金を後で回収する際に使用 |
|---|---|
| 未収金(みしゅうきん) | 商品売買以外の取引で代金を後で回収する際に使用 |
今回学習しているのは、商品売買で使用する「売掛金」です。
「未収金」は強化学習1-●で解説します。
仕訳の際に「売掛金」と「未収金」で迷わないようにしっかり違いを理解しておく必要があります。
勘定科目「売掛金」の所属グループ
勘定科目「売掛金」は「資産」の勘定科目に所属します。
基礎学習8で学んだ通り、資産のグループに属する勘定科目の定義は、【①現金・預金または②将来、お金やサービスを受け取る権利】です。
勘定科目「売掛金」の借方貸方
勘定科目「売掛金」は、「資産」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 資産の増加 | 必ず、借方に記録 |
|---|---|
| 資産の減少 | 必ず、貸方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
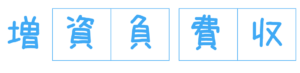
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
勘定科目「売掛金」の仕訳タイミング
日商簿記3級試験で出題される「売掛金」の仕訳のタイミングは次の3つです。
- 掛けで商品を売ったとき
- 売掛金を回収したとき
- 売掛金で売った商品が返品されたとき(売上戻し)
勘定科目「売掛金」の仕訳を例題とともに理解する
①掛けで商品を売ったとき
:売掛金(資産)が増えたときは左側の借方
基礎学習6で学んだ通り、資産の増加は必ず借方に記録をします。
例1)B商店に商品¥3,000を売り上げ、代金は掛けとした。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 売掛金 | 3,000 | 売上 | 3,000 |
【仕訳解説】
- 「商品¥3,000を売り上げ」と「代金は掛けとした」から商品販売の掛取引だと判断します。
- 「商品¥3,000を売り上げ」から「売上の増加」と判断します。
- 売上は「収益」の勘定科目なので、増加した場合には貸方に記録します。
- 商品を販売した代金を掛けとているので「売掛金の増加」と判断します。
- 売掛金は「資産」の勘定科目なので、増加した場合には借方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
②売掛金を回収したとき
:売掛金(資産)が減ったときは右側の貸方
基礎学習6で学んだ通り、資産の減少は必ず貸方に記録をします。
例1)取引先から売掛金¥4,000が当座預金に振り込まれた。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 当座預金 | 4,000 | 売掛金 | 4,000 |
【仕入解説】
- 今回は売掛金の回収が取引内容となります。
- 「当座預金に振り込まれた」から「当座預金の増加」と判断します。
- 当座預金は「資産」の勘定科目なので、増加した場合には借方に記録します。
- 今回、売掛金の回収が完了したので、お金を受取る権利がなくなります。よって、「売掛金の減少」の処理をします。
- 売掛金は「資産」の勘定科目で、減少した場合には貸方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
③売掛金で売った商品が返品されたとき(売上戻し)
:売掛金(資産)が減ったときは右側の貸方
基礎学習6で学んだ通り、資産の減少は必ず貸方に記録をします。
例2)得意先に販売した商品のうち30個(@¥1,000)に不良があるとして返品され、掛代金から差し引くこととした。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 売上 | 30,000 | 売掛金 | 30,000 |
【仕入解説】
- 今回は掛けで売り上げた商品の返品(売上戻し)が取引内容となります。
- まず、売り上げた商品の返品なので「売上の減少」の処理をします。
- 売上は「収益」の勘定科目なので、減少した場合には借方に記録します。
- 次に返品された分の代金は「掛代金から差し引く」とあるので、「売掛金の減少」の処理をします。
- 売掛金は「資産」の勘定科目で、減少した場合には貸方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
クレジット売掛金の詳細と仕訳
勘定科目「クレジット売掛金」とは?
クレジット売掛金とは、
売上取引の際に、商品代金の支払いがクレジットカードで行われた際に使う勘定科目のこと
売掛金とクレジット売掛金を別にする理由
「売掛金」と「クレジット売掛金」を別にする理由は、代金を受け取る相手が異なるためです。
通常の「売掛金」は、商品を販売した取引先(得意先)から商品代金を後から受け取る権利ですが、「クレジット売掛金」は、クレジットカード会社(信販会社)から商品代金をもらう権利になります。
| 売掛金 | 得意先からお金を受取る権利 |
|---|---|
| クレジット売掛金 | 信販会社からお金を受取る権利 |
なお、クレジットカードでの支払いで商品を販売した際には、クレジットカード会社(信販会社)に手数料を支払う必要があります。
勘定科目「クレジット売掛金」の所属グループ
勘定科目「クレジット売掛金」は「資産」の勘定科目に所属します。
基礎学習8で学んだ通り、資産のグループに属する勘定科目の定義は、【①現金・預金または②将来、お金やサービスを受け取る権利】です。
勘定科目「クレジット売掛金」の借方貸方
勘定科目「クレジット売掛金」は、「資産」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 資産の増加 | 必ず、借方に記録 |
|---|---|
| 資産の減少 | 必ず、貸方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
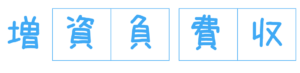
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
勘定科目「クレジット売掛金」の仕訳タイミング
日商簿記3級試験で出題される「クレジット売掛金」の仕訳のタイミングは次の2つです。
- クレジットカード支払いの条件で商品を売ったとき
- クレジット売掛金を回収したとき
勘定科目「クレジット売掛金」の仕訳を例題とともに理解する
①クレジットカード支払いの条件で商品を売ったとき
:クレジット売掛金(資産)が増えたときは左側の借方
基礎学習6で学んだ通り、資産の増加は必ず借方に記録をします。
例)B商店に商品¥3,000をクレジット払いの条件でを売り上げた。
なお、信販会社への手数料(販売代金の2%)は販売時に計上する。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 支払手数料 クレジット売掛金 |
60 2940 |
売上 | 3,000 |
※仕訳の縦の並びは仕訳解説に合わせています。金額とセットで上下逆でも問題ありません。
【仕訳解説】
- 今回はクレジットカード支払いの条件で商品を売ったときの取引です。
- まず、商品を販売しているので「売上の増加」の処理をします。
- 売上は「資産」の勘定科目で、資産の増加は借方に記録します。
- 次に信販会社への手数料を処理します。信販会社への手数料の勘定科目は「支払手数料」です。
- 支払手数料は費用の勘定科目で、増加の場合は借方に記載します。なお、金額は¥3,000円の2%、¥60です。
- 最後にクレジット売掛金(¥3000-¥60=¥2940)の処理をします。
- クレジット売掛金は「資産」の勘定科目で、資産の増加は借方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
②クレジット売掛金を回収したとき
:クレジット売掛金(資産)が減ったときは右側の貸方
基礎学習6で学んだ通り、資産の減少は必ず貸方に記録をします。
例)信販会社より決済手数料が差し引かれた残額¥2,940が当座預金口座へ入金された。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 当座預金 | 2,940 | クレジット売掛金 | 2,940 |
【仕訳解説】
- 今回はクレジット売掛金を回収したときの取引になります。
- まずは「当座預金口座に入金された」の処理をします。入金されたので「当座預金の増加」と判断します。
- 当座預金は「資産」の勘定科目で、増加した場合には借方に記入します。
- 次にクレジット売掛金の処理をします。入金によりクレジット売掛金の回収が完了したので、お金を受取る権利がなくなります。よって、「クレジット売掛金の減少」の処理をします。
- クレジット売掛金は「資産」の勘定科目で、減少した場合には貸方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
まとめ
*******
*******
*******
では、次の強化学習●で*****習得していきましょう。
強化学習●進む
| 前の学習へ戻る | 総合目次へ | 次の学習へ進む |