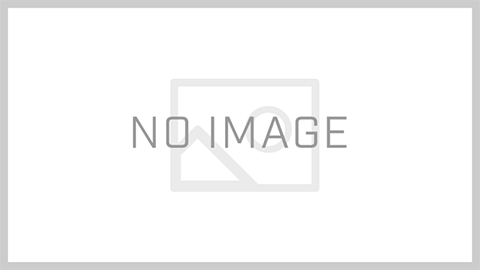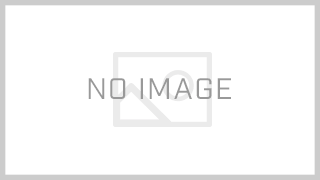強化学習1-5では、勘定科目が「●●」となる取引の仕訳について学びます。
商品売買の記帳方法について勉強します。商品売買の記帳方法はいくつかありますが、日商簿記3級では三分法と分記法が出題対象となります。
今回はこの2つの方法についてっ詳しく学んでいきましょう。
目次
そもそも、商品売買とは?
商品売買とは?
図
商品売買で覚えておきたい用語
| 用語 | 内容 |
| 仕入れ(しいれ) | 顧客に販売する商品を購入すること |
| 原価(げんか)/ 仕入原価(しいれげんか) |
仕入れたときの商品の金額のこと |
| 仕入先(しいれさき) | 商品を仕入れた取引先(相手先)のこと |
| 仕入戻し(しいれもどし) | 仕入た商品の品違いや注文数の間違い、あるいは商品に欠陥があった場合などにおいて、仕入た商品の一部またはその全部を仕入先(取引先)へ返品・返却すること |
| 売り上げ(うりあげ) | 顧客に仕入れた商品を販売すること |
| 売価(ばいか) | 販売したときの商品の金額のこと |
| 売上戻し(うりあげもどし) | 販売した商品の品違いや注文数の間違い、あるいは商品に欠陥があった場合などにおいて、販売した商品の一部またはその全部が返品・返却されること |
| 得意先(とくいさき) | 仕入た商品を販売した取引先(相手先)のこと |
商品売買の記帳方法は2種類(三分法と分記法)
日商簿記3級で出題される商品売買の記帳方法は次の2種類です。
【商品売買の2つの記帳方法】
- 三分法(さんぶんほう)
- 分記法(ぶんきほう)
2つの違いを最も簡単に言うなら、仕訳するときに使う勘定科目が異なるということです。
では、三分法と分記法の違いを解説していきましょう。
三分法と分記法の違い
先ほどもお伝えしましたが、2つの違いを最も簡単に言うなら、仕訳の際に使用する勘定科目が異なるということです。
三分法(さんぶんほう)とは?
三分法とは、
商品売買取引の仕訳を「仕入(費用) 」「売上(収益)」「 繰越商品(資産)」 の3つの勘定科目で記入する方法
※()内は勘定科目の所属グループ
分記法(ぶんきほう)とは?
分記法とは、
商品売買取引の仕訳を「商品(資産)」と「商品売買益(収益)」の2つの勘定科目で記入する方法
※商品売買益は商品販売益でもOK
※()内は勘定科目の所属グループ
まずは次のことが理解できていれば問題ありません。
- 三分法は、3つの勘定科目「仕入」「売上」「繰越商品」を使用する
- 分記法は、2つの勘定科目「商品」「商品売買益」を使用する
日商簿記3級試験での「三分法と分記法」の扱い
日商簿記3級は三分法がメイン
日商簿記3級試験では、三分法がメインです。
問題文で指定がない限り三分法(仕入・売上・繰越用品)を使って仕訳を行います。
なお、分記法はめったに出題されません。
過去16年45回の試験の内、4回しか出題されたことがなく、出題内容も単純な仕訳ではなく複雑な内容になっています。
なので、一所懸命に分記法を理解しようとするより、日商簿記試験で出題頻度の高い内容を先にしっかりマスターすることが重要となります。
本ページでも分記法については参考程度に解説します。
【過去に分記法が出題された試験】
ネット上で確認できる限り、過去16年間45回の日商簿記3級試験うち、分記法が出題されたのは次の4回。
- 第109回の第2問(2004年)
- 第113回の第2問(2012年)
- 第122回の第2問(2009年)
- 第133回の第2問(2006年)
4回すべてが第2問での出題で、分記法で記帳された商品勘定および商品売買益勘定、損益勘定から仕訳を考え、その仕訳を、三分法を用いて記帳するというもので、かなり難しい問題に部類されます。
勘定科目「仕入」の詳細と仕訳(三分法)
三分法で使用する勘定科目のうち「仕入」について解説していきます。
日商簿記3級で出題される基本中の基本なのでしっかり身に着けていきましょう。
勘定科目「仕入」とは?
勘定科目「仕入」とは、
商品の仕入額を表す勘定科目で、商品売買の記帳を三分法で行う場合に使用する
勘定科目「仕入」の所属グループ
勘定科目「仕入」は「費用」の勘定科目に属します。
基礎学習8の復習になりますが、費用のグループに属する勘定科目の定義は、
【事業を行うために支払ったお金のうち、負債の増加や資産の減少の要因そのもの】です。
勘定科目「仕入」の借方貸方
勘定科目「仕入」は「費用」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 費用の増加 | 必ず、借方に記録 |
|---|---|
| 費用の減少 | 必ず、貸方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
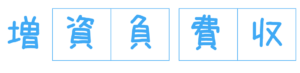
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
勘定科目「仕入」の仕訳タイミング
日商簿記3級試験で出題される勘定科目「仕入」の仕訳のタイミングは次の2つです。
- 商品を仕入れたとき
- 仕入た商品を返品した(仕入戻し)
勘定科目「仕入」の借方貸方を例題とともに理解する
それでは、例題を使って仕訳を理解していきましょう。
①商品を仕入れたとき
:仕入(費用)が増えたときは左側の借方
基礎学習6で学んだ通り、費用の増加は必ず借方に記録をします。
例)取引先より商品¥5,000を現金で購入した。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 仕入 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
【仕訳解説】
- 取引先から商品を購入しているので、「仕入の増加」と判断します。
- 仕入は「費用」の勘定科目なので、増加した場合には借方に記録します。
- 「現金で購入」とあるので「現金での支払い」つまり、「現金の減少」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、減少した場合には貸方に記録します。
- なお、複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
②仕入た商品を返品した(仕入戻し)
:仕入(費用)が減ったときは右側の貸方
基礎学習6で学んだ通り、費用の減少は必ず貸方に記録をします。
返品した場合には、購入した時に「仕入」で処理した分を減らす必要があるので、仕入の減少となります。
例)以前、現金払いで仕入れた商品のうち¥3,000分について不良が発見されたため取引先へ返品した。返品分した分の商品代金は返品と同時に現金で受け取った。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金 | 3,000 | 仕入 | 3,000 |
【仕入解説】
- 商品を返品しているので、今回の取引は仕入戻しだと判断します。
- 商品を返品したときには「仕入の減少」で処理します。
- 仕入は「費用」の勘定科目なので、減少した場合には貸方に記録します。
- 「返品分した分の商品代金は現金で受け取った」とあるので「現金の増加」で処理します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、増加した場合には借方に記録します。
- なお、複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
仕入戻しは、掛けで購入した商品の返品として出題されることが多いのですが、今回の強化学習1-5の段階では、掛け(買掛金)の学習していないので、あえて現金にしています。
勘定科目「売上」の詳細と仕訳(三分法)
勘定科目「売上」とは?
勘定科目「売上」とは、
商品の売却額を表す勘定科目で、
商品売買の記帳を三分法で行う場合に使用する
勘定科目「売上」の所属グループ
勘定科目「売上」は「収益」の勘定科目に属します。
基礎学習8の復習になりますが、収益のグループに属する勘定科目の定義は、【①商品・サービスを提供して得た儲け(収入)または②収入が増えた理由(原因)そのもの】です。
勘定科目「売上」の借方貸方
勘定科目「売上」は「収益」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 収益の増加 | 必ず、貸方に記録 |
|---|---|
| 収益の減少 | 必ず、借方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
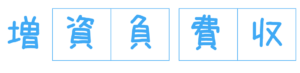
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
勘定科目「売上」の仕訳タイミング
日商簿記3級試験で出題される勘定科目「売上」の仕訳のタイミングは次の2つです。
- 商品を売ったとき
- 売った商品が返品されたとき(売上戻し)
勘定科目「売上」の仕訳を例題とともに理解する
それでは、例題を使って仕訳を理解していきましょう。
①商品を売ったとき
:売上(収益)が増えたときは右側の貸方
基礎学習6で学んだ通り、収益の増加は必ず貸方に記録をします。
例)得意先に商品¥5,000を掛けで販売した。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 売掛金 | 5,000 | 売上 | 5,000 |
【仕訳解説】
- 「得意先に商品を販売」とあるので「売上の増加」と判断します。
- 売上は「収益」の勘定科目なので、増加の場合には貸方に記録します。
- 商品の販売を掛けで行ったときの勘定科目は「売掛金」です。(売掛金の詳細は強化学習1-●で解説)
- 売掛金は、得意先(顧客)に商品やサービスを掛け(後払い)で販売した時に「後で得意先からお金を受け取る権利」のことを指し、「資産」の勘定科目になります。
- 掛けで売ったので、将来お金をもらう権利(売掛金)が増えたと考えるので「売掛金の増加」と判断します。
- 資産の増加は借方なので「売掛金」は借方に記録します。
- 複式簿記の借方貸方の金額は一致します。
②売った商品が返品されたとき(売上戻し)
:売上(収益)が減ったときは左側の借方
基礎学習6で学んだ通り、収益の減少は必ず貸方に記録をします。
例)得意先に現金で販売した商品のうち¥3,000分について不良が発見されたとして返品された。なお、返品された日に、返品分の代金を現金で支払った。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 売上 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
【仕訳の解説】
- 取引先に返品したので、売り上げたときと逆の仕訳(逆仕訳)を行います。
- 販売した商品が戻されたので、売上(収益)として帳簿に記録していた金額から返品された分を減らす必要があります。よって売上の返品は「売上の減少」で処理します。
- 売上は「収益」勘定科目なので、減少の場合には借方に記録します。
- 返品分の代金を現金で支払っているので「現金の減少」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、減少の場合には貸方に記録します。
- 複式簿記の借方貸方の金額は一致します。
売上戻しは、掛けで販売した商品の返品として出題されることが多いのですが、今回の強化学習1-5の段階では、掛け(売掛金)の学習していないので、あえて現金にしています。
勘定科目「繰越商品」の詳細(三分法)
勘定科目「繰越商品」とは?
勘定科目「繰越商品」とは、
期末(期首)の売れ残り商品(在庫商品)の原価を表す勘定科目で、
商品売買を三分法で記帳した際の決算時に使う
勘定科目「繰越商品」の所属グループ
勘定科目「繰越商品」は「資産」の勘定科目に属します。
基礎学習8の復習になりますが、資産のグループに属する勘定科目の定義は、【①現金・預金または②将来、お金やサービスを受け取る権利】です。
繰越商品は、決算時に残っている商品在庫の原価を表します。
商品在庫は、まだ商品としての価値を保持しており、来期に販売すればお金を受け取る権利を持っています。よって、繰越商品は資産と判断します。
勘定科目「繰越商品」の仕訳のタイミング
- 決算(決算整理仕訳)
→売上原価の算定 - 期首(再振分仕訳)
→「繰越商品」を「仕入」に振り替える
勘定科目「繰越商品」の仕訳
繰越商品の仕分けは、日常の仕訳とは異なり特別な仕訳(決算整理仕訳・再振分仕訳)となります。
仕訳の詳細は、強化学習●で詳しく解説します。
「分記法(商品・商品売買益)」の詳細と仕訳方法
今度は、日商簿記3級で出題される商品売買の記帳方法のうち、分記法で使用する勘定科目「商品」「商品売買益」に解説していきます。
※分記法はほとんど出題されないので、後回しにしてOKです。
分記法で使用する勘定科目「商品」の詳細
勘定科目「商品」とは?
勘定科目「商品」とは、
商品の原価(仕入原価)を表す勘定科目で、商品売買を分記法で記帳した際に使う
勘定科目「商品」の所属グループ
勘定科目「商品」は「資産」の勘定科目に属します。
勘定科目「商品」の借方貸方
勘定科目「商品」は「資産」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 資産の増加 | 必ず、借方に記録 |
|---|---|
| 資産の減少 | 必ず、貸方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
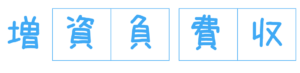
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
分記法で使用する勘定科目「商品売買益」の詳細
勘定科目「商品売買益」とは?
勘定科目「商品」とは、
売価と仕入原価との差額(売上総利益)を表す勘定科目で、商品売買の記帳を分記法で行う場合に使用する
勘定科目「商品売買益」の所属グループ
勘定科目「商品売買益」は「収益」の勘定科目に属します。
勘定科目「商品売買益」の借方貸方
勘定科目「商品」は「資産」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 資産の増加 | 必ず、借方に記録 |
|---|---|
| 資産の減少 | 必ず、貸方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
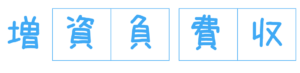
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
分記法の仕訳のタイミング
日商簿記3級試験のためには、次の2つのタイミングが最低理解できれば大丈夫です。
- 商品を仕入れたとき
- 商品を売ったとき
分記法の仕訳を例題とともに理解する
※分記法はほとんど出題されないので、後回しにしてOKです。
①商品を仕入れたとき
例)A社はB社から商品¥1,000を仕入、代金は現金で支払った。記帳は分記法でおこなうこととする。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 商品 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
【仕訳解説】
- 分記法でとかかれているので「商品」「商品売買益」の2つの勘定科目を思い出します。
- 商品の仕入で商品が増えるので「商品の増加」と判断します。
- 商品は「資産」の勘定科目なので、増加の場合には借方に記録します。
- 代金は現金で支払っているので「現金の減少」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、減少の場合には貸方に記録します。
- 複式簿記の借方貸方の金額は一致します。
②商品を売ったとき
例)A社はB社に商品(原価¥800、売価¥1000)を売り上げ、代金は現金で受け取った。記帳は分記法でおこなうこととする。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金 | 1,000 | 商品 商品売買益 |
800 200 |
【仕訳解説】
- 分記法でとかかれているので「商品」「商品売買益」の2つの勘定科目を思い出します。
- まず、勘定科目「商品」の処理をします。
- 商品を販売しているので、在庫商品が減ります。よって「商品の減少」と判断します。
- 勘定科目「商品」は、「資産」の勘定科目なので、減少の場合には貸方に記録します。
- なお、「商品」の金額は、仕入れた時の金額(仕入れ値)、つまり原価なので¥800です。
- 次に「商品売買益」の処理をします。
- 商品売買益の金額は、売価¥1,000-原価¥800なので¥200です。
- 商品売買益は「資産」の勘定科目なので、増加の場合には借方に記録します。
- 代金は現金で支払っているので「現金の減少」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、減少の場合には貸方に記録します。
- 複式簿記の借方貸方の金額は一致します。
まとめ
*******
*******
*******
では、次の強化学習●で*****習得していきましょう。
強化学習●進む
| 前の学習へ戻る | 総合目次へ | 次の学習へ進む |