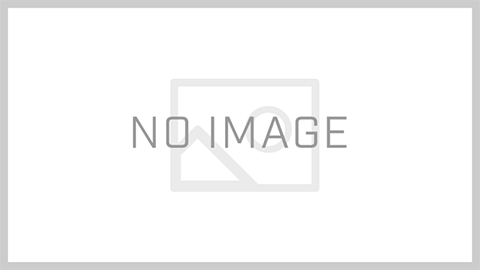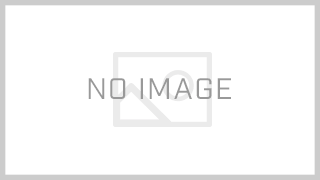強化学習1-1では、勘定科目「現金」の詳細と仕訳について詳しく学びます。
目次
そもそも、簿記上の「現金」とは?
日常生活で「現金」と言った場合には、通貨(紙幣と硬貨)を指しますが、簿記の世界で現金は通貨だけではありません。
簿記上の「現金」とは次の2つのこと
- 通貨
- 通貨代用証券(つうかだいようしょうけん)
簿記上の現金「通貨」と「通貨代用証券」の詳細
通貨とは?
通貨とは、
私たちが日常生活でお金と呼んでいる紙幣と硬貨のこと
通貨代用証券(つうかだいようしょうけん)とは?
通貨代用証券とは、
受け取ったら金融機関ですぐに換金できる証券のこと
※証券とは、財産法上の権利・義務について記載をした紙片のこと
日商簿記3級試験に出題される通貨代用証券の代表例
日商簿記3級試験では次の5つが通貨代用証券になります。
- 他人振出小切手(たにんふりだしこぎって)
- 送金小切手(そうきんこぎって)
- 郵便為替証書(ゆうびんかわせしょうしょ)
- 配当金領収証(はいとうきんりょうしゅうしょう)
- 期限到来公社債利札(きげんとうらいこうしゃさいりふだ)
「他人振出小切手」は日商簿記3級試験で出題頻度が高いので、仕訳方法までしっかり身に着ける必要があります。別途強化学習1-●で詳しく解説します。
ただ、残りの②~⑤は、細かい内容まで理解する必要はありません。
こういう名称が出てきたら勘定科目「現金」で処理するとが分かれば大丈夫です。
勘定科目「現金」の詳細と仕訳方法
勘定科目「現金」を一覧で確認
通貨と通貨代用証券は次の通りです。
現段階では、通貨代用証券はこの一覧にかかれた内容がなんとなく分かれば大丈夫です。
| 勘定 科目 |
内容 | 詳細 | |
| 現金 | 通貨 | 貨幣・硬貨 | 私たちが日常でお金と呼んでいるもの |
| 通貨代用証券 |
他人振出小切手 (たにんふりだしこぎって) |
小切手のうち、自分以外の他人からもらった小切手のこと。 | |
| 送金小切手 (そうきんこぎって) |
送金手段として、銀行で発行してもらう小切手のこと。小切手と違い当座預金をつくらなくても発行してもらえる。 | ||
| 郵便為替証書 (ゆうびんかわせしょうしょ) |
送金手段として、郵便局(ゆうちょ銀行)で発行してもらう証書。送金小切手の郵便局版。 | ||
| 配当金領収証 (はいとうきんりょうしゅうしょう) |
株式会社が配当金を配布する際に交付する引換証のこと。 | ||
| 期限到来公社債利札 (きげんとうらいこうしゃさいりふだ) |
公社債(国・地方公共団体・会社が資金調達をする際に発行する借用証書)についている利札(クーポン券のようなもの)のうち、支払期日に達しているもののこと。 | ||
勘定科目「現金」の所属グループ
勘定科目「現金」は「資産」の勘定科目に所属します。
基礎学習8で学んだ通り、資産のグループに属する勘定科目の定義は、
【①現金・預金または②将来、お金やサービスを受け取る権利】です。
勘定科目「現金」の借方貸方
勘定科目「現金」は、「資産」の勘定科目なので、複式簿記の借方貸方は次のようになります。
| 資産の増加 | 必ず、借方に記録 |
|---|---|
| 資産の減少 | 必ず、貸方に記録 |
仕訳に慣れるまでは、基礎学習6で学んだこの図をメモやノートに書くのがおすすめです。
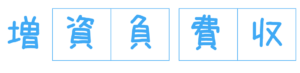
これが何か思い出せない方は、基礎学習6を後で復習してみてください。
勘定科目「現金」の仕訳のタイミング
日商簿記3級試験で出題される「現金」の仕訳のタイミングは大きく分けると次の2つです。
- 現金が増えた時とき
→通貨・通貨代用証券を受取ったとき - 現金が減ったとき
→通貨で支払い支払ったとき
→通貨を預金口座へ預け入れたとき
→通貨代用証券で支払ったとき
勘定科目「現金」の仕訳を例題とともに理解する
①現金(資産)が増えたときは左の借方
基礎学習6で学んだ通り、資産の増加は必ず借方に記録をします。
例1)商品¥5,000を販売し、代金を現金で受け取った。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金 | 5,000 | 売上 | 5,000 |
【仕訳の解説】
- 「代金を現金で受け取った」から「現金の増加」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、増加の場合は借方に記録します。
- 商品を販売した際の代金には、勘定科目「売上」を使います。販売しているので「売上の増加」と判断します。(勘定科目「売上」は強化学習1-●で解説します)
- 「売上」は「収益」の勘定科目なので、増加の場合は貸方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
例2)普通預金口座から現金¥3,000を引き出した。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金 | 3,000 | 普通預金 | 3,000 |
【仕訳の解説】
- 口座から現金を引き出すと、手元の現金が増えるので「現金の増加」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、増加の場合は借方に記録します。
- 普通預金口座の残高は、勘定科目「普通預金」を使います。
- 預金を引き出して残高が減っているので「普通預金の減少」と判断します。(勘定科目「普通預金」は強化学習1-●で解説します)
- 「普通預金」は「資産」の勘定科目なので、減少の場合は貸方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
例3)A商店に商品¥6,000を販売し、代金を同店振出の小切手で受け取った。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金 | 6,000 | 売上 | 6,000 |
【仕訳の解説】
- 「同店振出の小切手」とあるので「他人振出小切手」の仕訳だと判断します。※同店振出=A商店振出の意味
- 「他人振出小切手」の勘定科目は「現金」です。代金として受け取っているので「現金の増加」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、増加の場合は借方に記録します。
- 商品を販売した際の代金には、勘定科目「売上」を使います。販売しているので「売上の増加」と判断します。(勘定科目「売上」は強化学習1-●で解説します)
- 「売上」は「収益」の勘定科目なので、増加の場合は貸方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
※他人振出し小切手の詳細と仕訳は、本ページの「通貨代用証券① 「他人振出小切手」の詳細と仕訳」で詳しく解説しています。
②現金(資産)が減ったときは右の貸方
基礎学習6で学んだ通り、資産の減少は必ず貸方に記録をします。
例1)コピー用紙¥300を現金で購入した。コピー用紙は消耗品費勘定で処理をすることとする。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 消耗品費 | 300 | 現金 | 300 |
【仕訳の解説】
- 「現金で購入した」は「現金で支払い」なので、「現金の減少」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、減少の場合は貸方に記録します。
- 購入したコピー用紙は「消耗品費勘定で処理」とあるので勘定科目「消耗品費」を使用し、「消耗品費の増加」と判断します。(勘定科目「消耗品費」は強化学習1-●で解説します)
- 消耗品費は「費用」の勘定科目なので、増加の場合は借方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
例2)普通預金口座に¥3,000を預け入れた。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 普通預金 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
【仕訳の解説】
- 口座に預け入れをすると、手元の現金が減るので「現金の減少」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、減少の場合は貸方に記録します。
- 普通預金口座の残高は、勘定科目「普通預金」し、預金残高が増えるので「普通預金の増加」と判断します。(勘定科目「普通預金」は強化学習1-●で解説します)
- 「普通預金」は「資産」の勘定科目なので、増加の場合は借方に記録します。
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。
例3)B商店から商品¥6,000を仕入、代金を同店振出の小切手で支払った。
この取引内容は次のように仕訳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 仕入 | 6,000 | 現金 | 6,000 |
【仕訳の解説】
- 「同店振出の小切手」とあるので他人振出小切手」の仕訳だと判断します。※同店振出=A商店振出の意味
- 「他人振出小切手」の勘定科目は「現金」です。代金として支払っているので「現金の減少」と判断します。
- 現金は「資産」の勘定科目なので、減少の場合は貸方に記録します。
- 商品を仕入れているので勘定科目「仕入」を使し、「仕入の増加」と判断します。(勘定科目「仕入」は強化学習1-●で解説します)
- 「仕入」は費用の勘定科目なので、増加の場合には借方に記録します。金
- 複式簿記のルール通り借方と貸方の金額は一致します。と間違えやすいもの
現金と間違えやすいもの
日商簿記3級試験では、現金と判断を間違える可能性が高いものが出題されることがあります。
現金と間違えやすいものの代表例
日商簿記3級試験で、現金と判断を間違える可能性が高いものの代表例は次の4つです
- 切手
- ハガキ
- 収入印紙
- 自己振出小切手(じこふりだしこぎって)
今あげた①~④は現金ではありません。
特に④の自己振出小切手は要注意です。(自己振出し小切手は強化学習1-●で解説)
他人振出小切手は勘定科目「現金」で処理するので、試験では引っ掛け問題として出題されやすいので注意が必要です。
さて、同じ小切手なのにどうして勘定科目が違うのか意味不明だと思ってところかもしれませんね。
小切手は、誰が振り出したかで勘定科目が変わります。
小切手については、強化学習1-●で仕組みから仕訳の違いまで、まとめて解説しています。
現金と間違えやすいものの正しい勘定科目
日商簿記3級試験で、現金と判断を間違える可能性が高いものの代表例4つの正しい勘定科目は次の通りです。
現段階では、参考程度にしっておくのでOKです。
| 使用する勘定科目 | |
| 切手 | 「通信費(費用)」 ※決算時に未使用なら「貯蔵品」に振替 |
| ハガキ | |
| 収入印紙 | 租税公課(費用) ※決算時に未使用なら「貯蔵品」に振替 |
| 自己振出小切手 | 「当座預金(資産)」 |
まとめ
*******
*******
*******
では、次の強化学習1-2では「現金過不足の仕訳」について詳しく学びます。
| 総合目次へ | 強化学習目次へ | 次の学習へ進む |